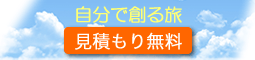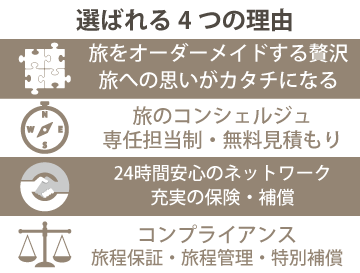別名"7つの丘の街"とも呼ばれる、ポルトガルの首都リスボン。
ヨーロッパの最西端に位置するこの町は、海のように広いテージョ川の河口に位置しています。
丘に囲まれていることから、石畳の道路や行き交う路面電車や素朴な街並みなどが近年人気になってきています。
リスボンの歴史は紀元前1000年頃にフェニキア人が港を築いた頃にまで遡ることができ、当時はテージョ川に守られた天然の良港だったこともあり“安全な港”という意味のアリス・ウーボと呼ばれていました。
その後のローマ時代、ムーア人による支配の時代と、支配者が変わる度に街は名前を変えました。
12世紀の中ごろに400年も続いたムーア人の支配から街を解放したのがアフォンソ・エンリケスです。
この時、街の名前が現在のリスボンと定められました。
そして15世紀、エンリケ航海王子によって幕が開いた大航海時代。
喜望峰を通ってインド大陸を発見したバスコ・ダ・ガマ、世界一周を指揮したフェルディナンド・マゼラン、アメリカ新大陸を発見したクリストファー・コロンブスなど、一度は教科書で学んだ面々が新たな世界を求めて旅立っていきました。
リスボン市街から少し離れた所にあるベレンには、こうした大航海時代の最盛期のポルトガルの名残を感じられる場所が残っています。
まず一つ目は、エンリケ航海王子の没後500年を記念して1960年に建てられた「発見のモニュメント」です。
テージョ川に面するこのモニュメントには、エンリケ航海王子を先頭に、大航海時代の探検家、芸術家・科学者・地図制作者・宣教師ら約30名のポルトガル人たちの姿が刻まれています。
新たに開拓された航路は、ポルトガルに多大な富をもたらし、海上帝国として大いに繁栄することになります。モニュメントの東側には日本とも繋がりが深いフランシスコ・ザビエルの彫刻も。
インド航路が発見されたことでポルトガルが海外交易に力を入れ始めた時期に王座につき、盤石な絶対王政を確立したのがマヌエル幸運王です。
ポルトガル黄金期の芸術様式「マヌエル様式」も彼の名から取られたもので、ゴシック様式を土台に、アフリカやアジアの珍しい動物や船や海に関係する、キリスト教を元にしたモチーフがあしらわれた独自のスタイルを確立しました。
過剰なまでに装飾をされた内装から、当時のポルトガルの繁栄ぶりを伺うことができます。
1983年にポルトガル初の世界遺産に登録されたもののうちの一つにベレンの塔とジェロニモス修道院があり、これらの建築にもマヌエル様式は用いられています。
ベレンの塔はテージョ川を行き交う船の監視と河口を守る要塞として、マヌエル幸運王の命によって1519年に建てられました。石灰岩で出来た塔は35mあり、地下から合わせて6層構造。
長く厳しい航海を終えて故国ポルトガルへと帰ってきた船員たちを出迎えるシンボル的な存在でした。塔の中は地下牢や砲台、レリーフが見事な国王の間、謁見の間など見どころが満載です。
ジェロニモス修道院はマヌエル様式の最高傑作とされ、1502年に着工してから完成するまでなんと300年もの歳月を費やしました。その建築資金はインド交易から持ち帰ったスパイスの売却で得た莫大な利益によって賄われました。
この修道院が完成してからは王家の霊廟もこちらに移され、マヌエル幸運王やヴァスコ・ダ・ガマ、有名な詩人・ルイス・デ・カモンイス、国民的作家・フェルナンド・ペソアらのお墓もこの修道院内にあります。
そしてこの修道院の中でも特に評価が高いのは、マヌエル様式の繊細な彫刻で飾られた回廊や、彫像で飾られたサンタ・マリア聖堂の2つ。大航海時代の栄華を是非ご堪能あれ!
ベレンの街を堪能したらバスコ・ダ・ガマ公園の向かい側にあるパステイシュ・デ・ベレンという、1837年創業のエッグタルト(パステル・デ・ナタ)が有名なお店で一休みするのもおススメです。
ポルトガルのカフェに欠かせないデザートで、元々のレシピはジェロニモス修道院の修道女が考え出したものだとも言われているんですよ!
■リスボン中心部からベレンまで
リスボン近郊鉄道カスカイス線ベレン駅下車またはトラム15E系統利用。
■各ホームページ
・VisitbelemHP(英語):http://www.visitbelem.pt/Default/en/Homepage
・ベレンの塔公式HP(英語):http://www.torrebelem.gov.pt/en/
・ジェロニモス修道院公式HP(英語):http://www.mosteirojeronimos.gov.pt/en/
・パスティシュ・デ・ベレンHP(英語):https://pasteisdebelem.pt/en/